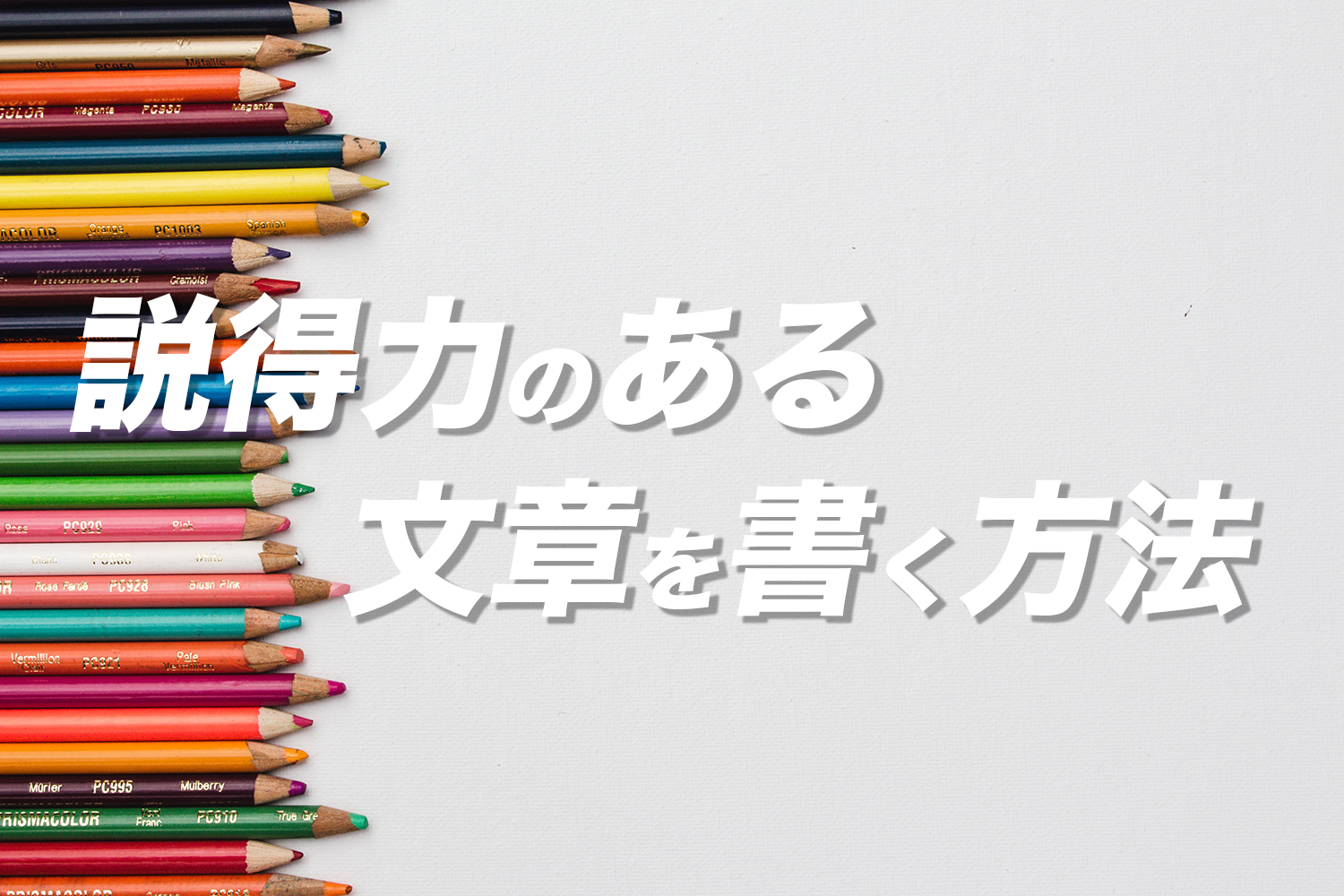【今日から使える】説得力のある文章を書く方法

初心者ブロガー「ブログ記事で説得力のある文章を書くにはどうしたらいいんだろうなぁ」
先ほどこのようなツイートをしました。
説得力のある文章を書くには
・目立たせる
・超シンプルに書く
・格言風にまとめる
・くり返して書く
これだけで説得力が大幅にあがります。
個人で稼ぐ時代には必須のスキルだとおもいます。
ブログはその訓練に最高のツールです。説得力のある文章を書くスキルは身につければ一石何鳥にもなります。— アヤノ@現場監督ブロガー (@ayanotoshiro) January 21, 2020
・目立たせる
・超シンプルに書く
・格言風にまとめる
・くり返して書く
これだけで説得力が大幅にあがります。
個人で稼ぐ時代には必須のスキルだとおもいます。
ブログはその訓練に最高のツールです。説得力のある文章を書くスキルは身につければ一石何鳥にもなります。
このような人におすすめの記事です。
- 説得力のある文章を身につけたい。
- ブログの記事に説得力を持たせたい。
- 説得力のあるプレゼンをしたい。
こんにちは アヤノです。
みなさんは人を説得させる文章が書けますか?
仕事でプレゼンをするとき。
ブログで情報を発信するとき。
人になにかをおすすめするとき。
説得力のある文章を書くスキルがあれば強みになりますよね。
この記事では説得力のある文章の書きかたについてお伝えします。
本記事の内容
- 文章を目立たせる。
- できるだけシンプルに書く。
- 格言風に仕立てる。
- 繰り返し書く。
- まとめ
スポンサードサーチ
説得力のある文章。

文章を目立たせる。
人は真実を信用するとは限らない。
真実を書いた文書には説得力があるのでしょうか。
答えはNOです。
たとえ真実を書いたとしても人はそれを信用するとは限りません。
書いた文章が真実かどうかは説得力には関係ないのです。
認知心理学者でノーベル経済学賞受賞者のダニエル・カーネマンは著書「ファスト&スロー」で説得力のある文章を書くには原則として認知負担(難しく思うこと)をできるだけ減らすことだと提言しています。
つまり「できるだけ見やすく、分かりやすく書くこと」です。
人は目立つものを信用する。
次の2つの文章を見比べてみてください。
- マハトマ・ガンディーは1857年に生まれた。
- マハトマ・ガンディーは1861年に生まれた。
上の文章はどちらも間違っていますが実験では太字で書いたほうが正しいと受けとられやすいという結果が出ています。
(マハトマ・ガンディーは1869年生まれです。)
他にも緑、黄、水色といった中間色よりも、明るい青、赤にするとより信用されます。
できるだけシンプルに書く。
簡単な言葉を使う。
自分を信頼できる知的な人間だと思ってもらいたいときは、できるだけ簡単な言葉を使うことです。
例えばあなたがパソコンショップに新しいパソコンを買いに行ったとしましょう。
パソコンについてよく知らないあなたに対して
- 専門用語をわざと多用して説明する店員。
- 専門用語をかみ砕いてわかりやすく説明する店員。
どちらが賢くて信用できる店員だと思いますか?
後者のわかりやすく説明してくれる店員のほうではないでしょうか。
ありふれた言葉を勿体ぶった言葉で表現すると知性に乏しく信憑性が低いとみなされてしまいます。
できるだけ簡単な言葉を使うことで、相手の認知負担(難しく思うこと)を減らしてあげるのです。
格言風に仕立てる。
リズムのよい文章にする。
文章はできるだけシンプルにした上で、リズムのよい文章にするとさらに説得力があると受けとられやすくなります。
ではリズムのよい文章とはどんなものなのか。
それは格言風の文章にすることです。
- 「読書は最高の時間短縮である。」
- 「読書は著者の膨大な努力と経験を本を読むことによって短時間で得ることがでる。」
さて、どちかが洞察に富む文章だと感じるでしょうか。
ある有名な実験では、
参加者の半数にあまり見慣れない格言を十数項目読ませました。
残りの半数にはおなじ内容をふつうの文章で読ませました。
すると格言風に仕立てた文章のほうが洞察に富むと判断されました。
発音しやすいだけで信用されやすい。
もうひとつ面白い実験をご紹介します。
ある実験では、
トルコの架空の企業について、2つの証券会社が提出した報告書に基づいて将来性を判断するよう参加者に指示しました。
証券会社の名前は、1つは発音しやすい「アルタン」、もう一つは厄介な「ターフート」。
2冊の報告書は、いくつかの項目で不一致をきたしていました。
このようなときは両者の中間をとるのが妥当と考えられますが、被験者は概ねターフートよりアルタンを信用しました。
つまり説得力は文章のみならず、発音さえもわかりやすいものを使ったものがよいということです。
例えば
- 参考文献を引用をするときは発音しやすい人が書いたものを選ぶ。
- プロジェクトに名前をつけるときは語呂がよいものにする。
「本当に発音まで説得力に関係あるの?」と思われるかもしれません。
しかし考えてみると成功した人物や企業はみんな発音しやすかったり語呂がよかったりしませんか?
それだけで成功したわけではないでしょうが、もしかしたら要因のひとつなのかもしれませんね。
繰り返し書く。
人はなじみのあるものを信用する。
人は見たことがあったり、聞いたことのあるものになじみを感じます。
これは文章でもおなじです。
例えばCMではおなじようなフレーズをなんどもくり返していたり、テレビショッピングでは売り文句をなんどもくり返して商品を紹介していますよね。
ある実験ではメッセージを10回くり返すと説得力が82%まで上昇するとうデータがあります。
「でもそんなにくり返していたら飽きられるのでは?」と心配になりますよね。
確かに全くおなじフレーズをくり返すと効果は上がりません。
しかし、おなじ内容のメッセージを言いまわしのバリエーションを変えて伝えることを意識すればOKです。
例えば「この本を買ってほしい」というメッセージであれば
- あの人も推薦!
- 売り切れ御免!
- アマゾンランキング10週連続一位!
というような感じです。
「この」「あの」「その」はつかわない。
もうひとつのテクニックとして「この」「あの」「その」はできる限りつかわないようにしましょう。
「この」「あの」「その」は指示代名詞として多用されがちですが、説得力のある文章を書くという点からいえば勿体ないことをしています。
メッセージを10回くり返すと説得力が82%まで上昇するとうデータがあるように、不自然でなければおなじフレーズをくり返したほうが説得力の効果が上がります。
「単純接触効果」
単純接触効果とはくり返されると好きになるという効果です。
生きものは自然界では危険にさらされています。
はじめて経験することは警戒します。
しかしおなじ経験をなんどくり返しても悪いことが起きないと、警戒心はうすれそれは安心に変わります。
説得力のある文章の裏づけには、私たちが生きのびできたルーツが関わっているのだと思うと感慨深いものがありますね。
スポンサードサーチ
まとめ【個人で稼ぐ時代の必須スキル】
これからは個人で稼ぐ時代です。
そのためには当然SNSやネットで情報を拡散させなければなりません。
しかし情報を拡散させるには説得力のある文章やことばをつかうスキルが必要ですよね。
みなさんもこれからはじまる新たな時代に備えて「説得力のある文章の書きかた」を身につけてみてはいかがでしょうか。
人気記事ここに記事タイトル